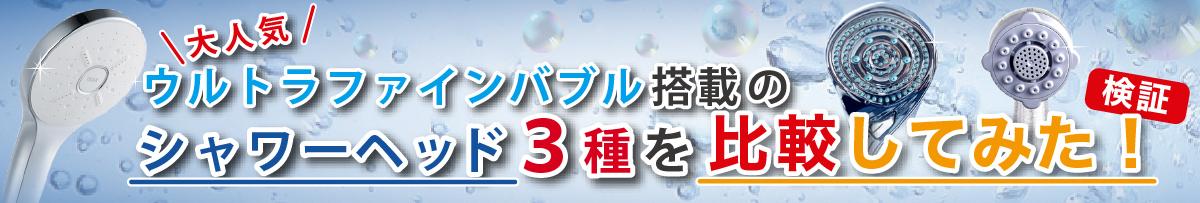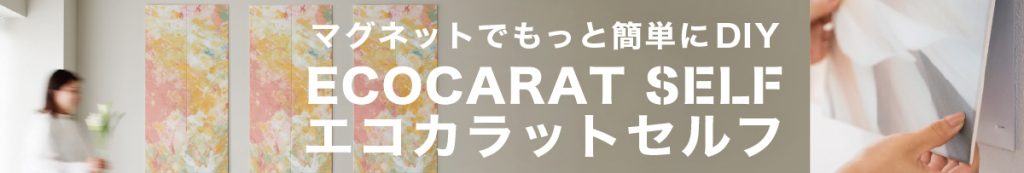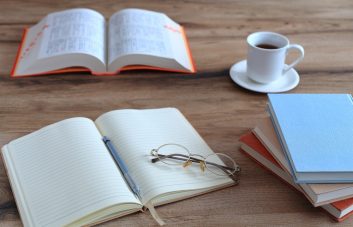もうすぐ5月5日『こどもの日』です。“端午の節句”とも呼ばれるこの日には、鯉のぼりや五月人形を飾って子どもの成長をお祝いします。五月人形は種類が多く、どれを選ぶか迷いがちですが、それと同じくらい「誰が贈るか」についても迷ってしまいますよね。
そこで今回は五月人形について、一般的に誰が買うべきか、その地域の風習や時代による違いを解説していきます。また端午の節句や五月人形の意味・由来、五月人形の種類や金額の目安なども合わせて載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
◯五月人形は誰が買うべき?
・昔は母方の祖父母が贈るのが風習だった
・地域による風習の大きな違い
・現在では家族の事情に合わせることが多い
【注意】五月人形の購入について事前に確認すること
◯端午の節句について
・端午の節句に込められた想いとその由来
・五月人形を飾る意味
・鯉のぼりを飾る意味
・五月人形や鯉のぼりを飾るのはいつからいつまで?
◯五月人形の選びかた
・大きさで決める
・価格で決める
・五月人形の種類
1.鎧飾り
2.兜飾り
3.子供大将飾り
4.収納飾り
5.ケース飾り
・男兄弟がいる場合は、人数分用意してあげるのがベスト
・五月人形が購入できるお店
【豆知識】五月人形はいつまでに購入すべき?
◯まとめ
・昔は母方の祖父母が贈るのが風習だった
・地域による風習の大きな違い
・現在では家族の事情に合わせることが多い
【注意】五月人形の購入について事前に確認すること
◯端午の節句について
・端午の節句に込められた想いとその由来
・五月人形を飾る意味
・鯉のぼりを飾る意味
・五月人形や鯉のぼりを飾るのはいつからいつまで?
◯五月人形の選びかた
・大きさで決める
・価格で決める
・五月人形の種類
1.鎧飾り
2.兜飾り
3.子供大将飾り
4.収納飾り
5.ケース飾り
・男兄弟がいる場合は、人数分用意してあげるのがベスト
・五月人形が購入できるお店
【豆知識】五月人形はいつまでに購入すべき?
◯まとめ
五月人形は誰が買うべき?

確かに風習としては残っていることもありますが、それは結婚後の実家との関わり合いを考慮してで生まれたものであり、そうした方が当時は折り合いが良かったのだと考えられます。
昔は母方の祖父母が贈るのが風習だった
一昔前は、結婚すると妻が夫の実家に同居する場合が多く、妻の両親はなかなか娘や孫に会う機会がありませんでした。そのため端午の節句には妻の両親が五月人形をお土産に、娘や孫に会いに行くのが定番になっていました。それが段々風習として定着していったのだと考えられます。
地域による風習の大きな違い
五月人形を誰が贈るかについては、同じ日本の中でも
・北海道/関東地方:父方の実家が贈る
・関西/九州地方:母方の実家が贈る
など地域によっては真逆の風習が根付いており、また地区町村や家系などで独自のルールを設けていることもあります。
現在では家族の事情に合わせることが多い
現在は大きく生活様式が変わり、結婚しても親と同居せず夫婦で暮らすケースや、夫の実家に入っても妻の両親に気軽に会いに行けるといったケースがかなり多くなりました。
なので五月人形においても、昔の風習に則るのではなく、現在の生活状況や親・祖父母の気持ちなどを総合的に判断して、最善の方法を考える必要があるでしょう。
例:両家でお金を出しあって共同で購入する
子供の両親が購入する
実家からお金を預かり、子供の両親がどれを買うか決める
【注意】五月人形の購入について事前に確認すること
昔の風習を大切にしている家庭と、現在の状況によって誰が購入するか決めたいと思っている家庭が混在している状況です。そのため、初めて端午の節句をお祝いする場合は、あらかじめ両方の実家としっかり話し合い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
親に贈ってもらう場合には、部屋のスペースを考慮した五月人形の大きさや、価格、飾りの種類、郵送時期なども合わせて相談しておきましょう。
昔の風習を大切にしている家庭と、現在の状況によって誰が購入するか決めたいと思っている家庭が混在している状況です。そのため、初めて端午の節句をお祝いする場合は、あらかじめ両方の実家としっかり話し合い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
親に贈ってもらう場合には、部屋のスペースを考慮した五月人形の大きさや、価格、飾りの種類、郵送時期なども合わせて相談しておきましょう。
端午の節句について

端午の節句に込められた想いとその由来
端午の節句は、春秋戦国時代の中国に生きた屈原(くつげん)という人物にまつわる故事が起源だとされています。
詩人・政治家である屈原は人望が厚く優秀で、国王の側近として勤めていたほどだった。しかし陰謀により国から追放されてしまい、放浪の身に。その後、祖国が滅びゆく未来を嘆いて、ついにある年の5月5日、川に身を投げてしまった。人々は屈原を供養するために、この日を祭りとして残した。
江戸時代、端午の節句を象徴する菖蒲の花と、尚武(武道を重んじること)の読みが一緒であることから、端午の節句は「男の子の誕生を祝い、強く育つように祈る日」へと変化しました。やがて幕府内で男の子が生まれると、馬印(武将が己の所在を示すために長柄の先に付けた印のこと)や幟を立ててお祝いするようになり、これを庶民が真似したことから、武者人形や鯉のぼりが誕生します。
そして現在、端午の節句は「こどもの日」に制定され、
“子供の人格を重んじ、子供の幸福をはかるとともに、母に感謝する日”
引用元:国民の祝日に関する法律 第2条となりました。性別関係なく、子供全員をお祝いする日として親しまれています。
ちなみに「端午の節句」という言葉は、「端(=はじめ)」の「午(=うま)」の日を指していて、言葉が示す通り、初期は毎月行う行事でした。そのうち「午」を「五」と置き換えるようになり、やがて3月3日の桃の節句と同じように、端午の節句も月日を揃えて5月5日になったようです。
リンク
五月人形を飾る意味
五月人形のモチーフである鎧や兜は”敵の攻撃から身を守るもの”であることから、さまざまな厄災から身を守ってくれる「お守り」としての意味が込められています。
リンク
鯉のぼりを飾る意味
鯉のぼりを飾るのには、天の神様に男の子の誕生を知らせ、子供の健やかな成長や将来の出世を願うという意味があります。
なぜ鯉なのかというと、鯉が滝を登り龍になった有名な「登竜門伝説」にちなみ、昔の人が立身出世のモチーフに選んだからです。
リンク
五月人形や鯉のぼりを飾るのはいつからいつまで?
地域により異なりますが、春分の日〜5月半ばごろを目安に飾るのが良さそうです。
春分の日から飾るのは少し早いと思った場合は、4月下旬あたりから飾り始めると季節が感じられるのでおすすめです。また片付けについては、梅雨の時期になるとカビが生える可能性があるので、できれば5月半ばの天気が良い日に、しっかり乾燥させてから片付けましょう。
五月人形の選びかた

大きさで決める
賃貸などの場合、大きな五月人形では部屋のスペースを取りすぎる可能性があります。このような失敗がないよう、あらかじめ飾る場所を決めておいて、そこに収まるサイズを把握しておくことが大切です。また親に購入してもらう場合にも、サイズを忘れずに伝えましょう。
価格で決める
五月人形は素材や製作過程などによって、数千円〜数十万円以上まで金額に大きな幅があります。とはいっても現在は実店舗・ネットなど多くの場所で五月人形が販売されており、選択肢がたくさんあるので、無理のない金額でより理想に近いものを探してみてください。
五月人形の種類
五月人形には大きく分けて以下の5種類があります。それぞれの説明に加えて専門店での金額の目安も記載しているので、合わせてご覧ください。
1.鎧飾り
五月人形の中で最も迫力があり、豪華なつくりが特徴です。主に源平時代の鎧を模した「大鎧」と、戦国時代の鎧を模した「銅丸鎧」の2つが主流ですが、そのほか有名な戦国武将の鎧を模したものもあります(武田信玄・徳川家康など)。飾るには広めのスペースが必要です。
[ 予算:約10万〜60万円 ]
リンク
2.兜飾り
兜飾りはサイズのバリエーションが多く、どのご家庭でも選びやすいのが魅力です。豪華な装飾を施したもの、和紙や革で仕立てたものなど、色々な種類が展開されています。
[ 予算:約5万〜30万円 ]
リンク
3.子供大将飾り
可愛らしくも凛々しい子供の人形に鎧が着せてあるタイプの飾りです。「五月人形」と聞いてこれを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。可愛らしさもあり人気が高いです。武者人形とも言われています。
[ 予算:約10万〜20万円 ]
リンク
4.収納飾り
兜や道具を飾り台に収納できるコンパクトな収納飾りは、しまっておく場所に困らないのが嬉しいポイントです。また土台に高さがあるため、直接床に飾っても違和感がありません。
[ 予算:約8万円〜20万円 ]
リンク
5.ケース飾り
人形や鎧・兜が透明のケースに入っているタイプです。中身が固定されていて、そのままの状態で飾ることができるので手間なく便利です。ケースに入っているため、人形が汚れないのも利点です。
[ 予算:3万〜10万円 ]
リンク
男兄弟がいる場合は、人数分用意してあげるのがベスト
五月人形は子供の身代わりとして、降りかかる厄災から守ってくれると信じられています。そのため、長男用として飾った五月人形を次男に流用すると、お守りとしての効果が薄れるだけでなく、それまで人形が代わりに受けた厄災を次男が引き継ぐことにもなりまねません。
昔は家の後継となる長男だけに五月人形を贈っていたこともありましたが、現在は一人ひとりに分け隔てなく贈ってあげるのが良いとされています。
もちろん小さなものでも問題ありませんので、”1人につき1つ”用意してあげてくださいね。
リンク
五月人形が購入できるお店
五月人形を取り扱っている主なお店に「専門店」「量販店」「ネットショップ」の3つがあります。詳しい説明を聞きながらじっくり選びたい人は専門店、手頃な値段で購入したいなら量販店が良いでしょう。
また五月人形を初めて購入する場合や、とにかく色々な商品を見比べたいという方には、色々なネットショップを巡ってみることをおすすめします。実店舗にはないハンドメイドの作品なども多数出品されているので、特別な一点モノを探している人にも最適です。
日本最大級のハンドメイドサイト「minne(ミンネ)」では、意匠を凝らした世界にひとつだけの五月人形がたくさん出品されています。誰とも被らないものが欲しい人、優しい雰囲気の作品を探している人は、ぜひ一度覗いてみてください。

こちらは和紙の千代紙で作られた、凛とした佇まいが美しい五月人形(武者人形)です。男子の健やかな成長への願いを込めて、弓や槍を持たせました。服の模様が人形ごとに違っており、「一点モノ」ならではの魅力が感じられます。また”縁起物”として、出産祝いや新築祝いのプレゼントにも選ばれています。
▶︎他の武者人形はこちら
【豆知識】五月人形はいつまでに購入すべき?
五月人形を買う時期に決まりはありませんが、3月〜4月中に購入しておくと長く楽しめます。店頭には3月3日のひな祭りを過ぎたあたりから並び出す場合が多いので、早めに購入したい場合は3月上旬から可能です。
五月人形を買う時期に決まりはありませんが、3月〜4月中に購入しておくと長く楽しめます。店頭には3月3日のひな祭りを過ぎたあたりから並び出す場合が多いので、早めに購入したい場合は3月上旬から可能です。
まとめ
一口に「五月人形」と言っても、かっこいいものから可愛らしいものまで多種多様です。予算や大きさはもちろん、見た目も良いものを選んであげたいですよね。最近では、手作りならではの暖かみが感じられるハンドメイドの五月人形にも注目が集まっています。ぜひこの機会にチェックしてみてください!