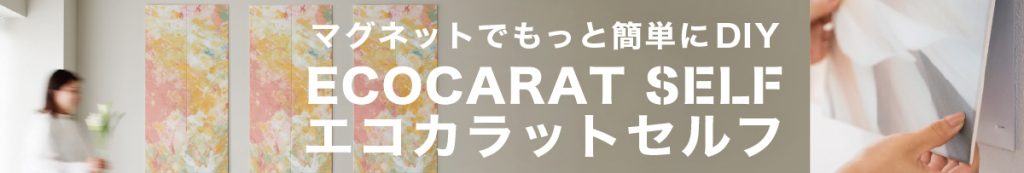節分は古くから行われている日本の風習ですが、その意味や由来を詳しく知っていますか?
最近ではあまり注目されなくなっていますが、子どもや海外の方にきちんと意味を教えてあげられる大人でいたいものです。
そこで今回は、節分・豆まきの意味や由来、節分と恵方巻の関係、さらに地方ごとの特色などもまとめて紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも節分って何?意味は?

そもそも節分とは「季節を分ける」という意味で、旧暦では春から新しい年が始まったため、立春の前日の節分(2月3日頃)は、大晦日に相当する大事な日でした。こういった理由から、春の節分が特に重要視されたのです。
ちなみに立春は「太陽黄経が315度になった日」とされていて、国立天文台の観測によって決められています。つまり天体の動きを軸に日程が決まるため、毎年日付が異なるのが特徴です。
2.なぜ豆まきをするの?

鬼は邪気や厄の象徴とされ、形の見えない災害、病、飢饉など、人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業だと信じられていたのです。節分の豆まきは、その邪気を追い払う行事として行われるようになりました。
なぜ”豆”なのかというと、「穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっている」という信仰があったからです。さらに「魔目(豆・まめ)」を鬼の目に投げつけて鬼を滅する=「魔滅」という語呂合わせから、鬼に豆をぶつけることで邪気を追い払い、一年の無病息災を願うようになったといわれています。
また、まかれた豆を自分の年齢の数だけ食べるという行為には、体が丈夫になり、風邪を引かないという意味が込められています。

ちなみに鬼は鰯の生臭い臭いと、柊のトゲが大の苦手とされていて、柊鰯(ひいらぎいわし)は柊の葉の棘が鬼の目を刺すので門口から鬼が入れず、また塩鰯を焼く臭気と煙で鬼が近寄らないと言われています。
その名残から、西日本では節分に鰯を食べる「節分いわし」の習慣が広く残っています。
3.各地の豆まきについて

通常、豆まきは「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆をまくのが一般的ですが、まく豆の種類は地域によって異なります。
関東以南の家庭では煎り大豆が定番で、北海道・東北・北陸・南九州では落花生が多いようです。落花生がまかれるのは「大豆より拾いやすく、地面に落ちても実が汚れない」「雪の中でも見つけやすい」などの合理的な考え方や地域の環境が理由となっているようで、なるほど、雪国が多いですね!
また、鬼が悪者を退治するなどの言い伝えがある地域や社寺では「鬼は外」とはいわず、「鬼は内」というところもあります。「九鬼さん」「鬼頭さん」など、苗字に鬼がつく家でも同様に「鬼は内」などといって、鬼を中に呼びこみます。
ご家庭で豆まきをする場合、お父さんが鬼役をして子供が豆をまくことが多いですよね。でも本来は父親、あるいは年男が豆をまいて鬼を追い払うのが正しい行いです。今年はお父さんに鬼役ではなく、豆をまかせて(任せて!)あげてみてはいかがでしょうか!
4.恵方巻と節分の関係は?

恵方巻の発祥は、戦前に大阪の寿司商組合がはじめたとされており、戦後に海苔問屋協同組合と組んで「幸運巻寿司」を売り出しました。
つまり節分と恵方巻には、実は歴史的な関係がありません。バレンタインデーのような企業の販促活動だったのです。
そもそも恵方巻の「恵方」とは、歳徳神(としとくじん)という神様のいる場所を指す言葉です。歳徳神はその年の福徳(金運や幸せ)を司る神様の事で、居場所が毎年変わります。そのため恵方巻は、その年の恵方を向いて丸かじりするわけです。
2023年の恵方の方角は、南南東です。今年は南南東を向いて恵方巻きを食べましょう。
なぜ1本丸々を無言で食べきるかというと、恵方巻きを切る行為は「縁を切る」とされ、恵方巻を口から離す行為は「福が逃げる」とされているからです。とはいえ無理は禁物ですので、自分のできる範囲でチャレンジしてみてくださいね。
恵方巻を食べる習慣は比較的新しくできたものですが、お祭りや行事の際に、寿司を食べるという習慣は昔からあります。昔は「発酵」というのは神様のお恵みとして、神様が作って与えてくれるものとして考えられてきました。寿司は昔から格の高い食べ物で、晴れの日の料理です。日本酒がお神酒として神事に使われるのも、そうした理由からなのです。
5.まとめ
今回は日本特有の風習である「節分」について、その意味や豆知識などを詳しくご紹介しました。 特に由来や恵方巻との関係については、知らなかった、また気にしたことすらなかったという方も多いのではないでしょうか?
節分はあまり目立つ行事とはいえませんが、「健康で良い一年を願う」という大切な意味を持つことを知っていただけると幸いです。
「節分」は家庭内で準備も簡単に出来るので、今年はイベントのひとつとして、ぜひご家族で楽しんでみてください。